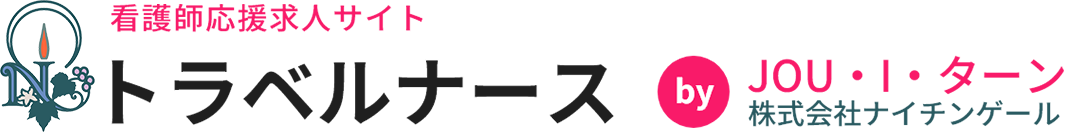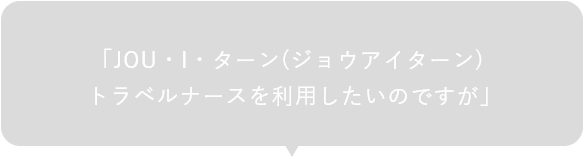2025.04.16
保健師と看護師の違い

保健師と看護師は、どちらも「保健師助産師看護師法」に基づく国家資格です。共に人々の健康を支える仕事ですが、その職務内容や活動範囲には違いがあります。
本記事では、保健師と看護師の違いについて分かりやすく解説します。
保健師と看護師の資格の違い

看護師の資格を取得するには、専門学校や短期大学で3年間、看護大学では4年間、高校の看護科から進学する場合は専攻科を含めて5年間学び、卒業後に看護師国家試験に合格する必要があります。
一方、保健師の資格を取得するには、保健師国家試験に合格しなければなりません。
受験資格を得るためには、文部科学大臣が指定する大学や養成課程で1年以上、保健師に必要な科目を履修するか、厚生労働大臣が指定する保健師養成所を卒業する必要があります。
これまでは、まず看護師の免許を取得した後に、保健師の免許を取得するのが一般的でした。
しかし現在では、高校卒業後に大学で看護師と保健師それぞれの専門課程を履修し、4年間の学びを経て、両方の国家試験を同時に受験できるカリキュラムが整えられており、人気を集めています。
この制度により、看護師と保健師の国家資格を同時に取得することが可能となり、国家試験に合格すれば、大学卒業後すぐに保健師として就職することもできます。
保健師と看護師の業務内容の違い

保健師と看護師の大きな違いは、看護師が「病気や怪我を負った患者の治療やケアを行う」のに対し、保健師は「病気や怪我を予防し、健康を維持・増進する活動を行う」という点にあります。
保健師は、病気や怪我をした人だけでなく、健康な人も含め、すべての人が長く健康に暮らせるようサポートする仕事です。
看護師と同様に、解剖学や生理学、臨床医学などの専門知識を学ぶほか、公衆衛生、社会保障制度、感染症や生活習慣病の予防など、より広い視点で人々の健康を支えるための知識を身につける必要があります。
また、勤務体制にも違いがあります。看護師が多く働く病院では、入院患者を24時間体制でケアする必要があるため、夜勤や休日出勤が多いのが一般的です。
一方、保健師は自治体や企業などで勤務することが多く、基本的に夜勤はなく、規則的な勤務時間の職場が多いのが特徴です(ただし、一部の職場では例外もあります)。
働き方の違いとして、看護師は立ち仕事が中心であるのに対し、保健師はデスクワークの比率が高い点も挙げられます。
保健師の業務には、検診データの入力・分析、報告書作成、健康教室の企画・運営なども含まれ、予防医療や健康管理の面から人々を支える重要な役割を担っています。
保健師と看護師の勤務地の違い

看護師の主な勤務先は、病院やクリニックなどの医療機関が中心ですが、2000年以降、介護保険制度の施行により、介護施設や訪問看護の分野でも活躍の場が広がっています。
また、保育園や企業の健康管理部門などで働く看護師も増えていますが、依然として医療・介護分野での勤務が大半を占めています。
保健師の勤務先は多岐にわたります。
主に、保健所、市区町村の役所、国民健康保険組合、看護支援センター、企業の健康管理部門、学校の保健室などで働き、地域住民や企業の従業員、学校の生徒などを対象に、健康管理や保健指導を行います。
また、病院で勤務する保健師もいます。病院では看護師と同様の業務を担当することもありますが、特に健診センターのある病院では、保健指導や健康管理の専門知識を活かした業務を行うことができます。
近年、企業の健康経営や予防医療への関心が高まる中、産業保健分野での保健師の需要も増えています。
期待される保健師の活躍

保健師の仕事は、大きく「行政保健師」「産業保健師」「学校保健師」の3つに分類されます。
●行政保健師:自治体の保健センターや役所に勤務し、地域住民の健康相談、母子保健、生活習慣病予防、感染症対策などを担当します。
●産業保健師:企業の健康管理部門で働き、従業員の健康診断のサポートやメンタルヘルスケア、労働環境の改善などを行います。
●学校保健師:学校に勤務し、学生や教職員の健康管理、保健指導、応急処置などを担当します。
このほかにも、JICA(国際協力機構)やNGOのスタッフとして発展途上国で保健・教育活動に携わる保健師や、高齢者の健康管理や介護予防を専門とする保健師も増加しています。
社会の健康意識の高まりとともに、保健師の求人は増加傾向にあります。
また、女性が多い職種であり、結婚や出産後も働きやすい環境が整っているため、離職率が比較的低いことも特徴の一つです。
さらに、企業や行政機関に属さず、フリーランスとして独立開業する保健師も増えています。
特に、独居高齢者の支援、地域密着型の介護・福祉サービス、健康教育活動など、保健師が活躍できる場は年々広がっています。